|
|
 |
|
|
|
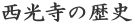 |
西光寺は今から約800年前、地頭、長谷部氏の助成で建仁元年(西暦1201年)鎌倉幕府、源頼朝の勅願寺として「天下泰平を怠ることなく拝みなさい」と建立されました。
安貞2年(西暦1228年)には、長谷部信連より五段の給田の寄付。天正8年(西暦1580年)には、温井景隆より土地の寄付。(輪島市史より)があり、由緒ある寺院であることが伺えます。
また、本堂については、上時国家を1808年〜1831年の竣工まで24年をかけて建築したと言われております、町野町のやすこ(安幸)の親方にあたる、柳田村の石井の万九郎が建築しました。
万九郎は、京都東本願寺の建立のおり、弟子を連れて仕事に行き(1835年)飛騨の匠と言われておりました。
西光寺の本堂の特徴は、遠近法建築で建てられており、柱の太さを微妙に変えることで、奥行きがあり、ご本尊を中心として放射線状に広がりを見せております。
西光寺の開山は不明、資料では建久8年(1197)南志見村の西光寺境内と敷地田の殺生と樹木伐採を禁じた地頭長谷部信連禁制案(長家文書)が存在することから、創建前の年号であるので、平家を監視する拠点として在った寺院を再興したとの見方もある。
言い伝えでは、現在地より山に上がった所に本堂があり、当時、七堂伽藍があったと言われ、近くの田んぼには、「大門」と呼ばれる地面がある。
また、近所の姓で「地蔵」「古坊」など寺院に関係した姓がある。 |
|
|

